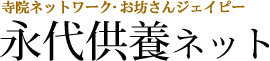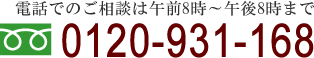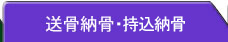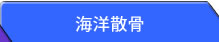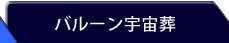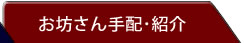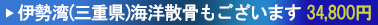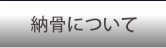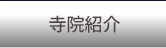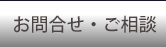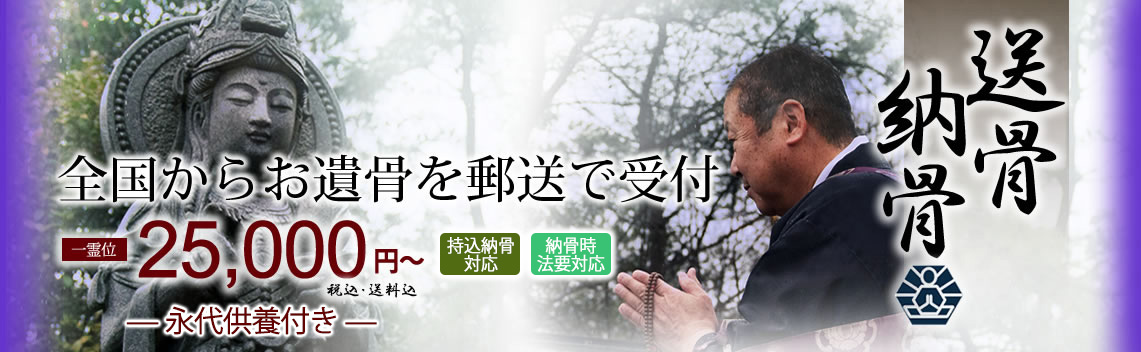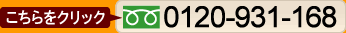【送骨納骨】納骨は寺院様にお任せいただく事となります。
【持込納骨】事前にご予約が必要になります。詳しくはご相談ください。
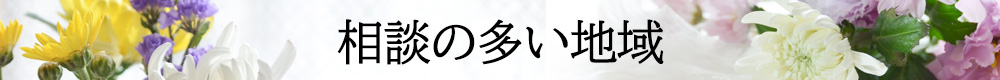
※下記地域には登録寺院がありませんので上記地域よりお選び下さい。
北海道,茨城,富山,石川,山梨,長野,奈良,山口,徳島,香川,高知,長崎,宮崎,鹿児島
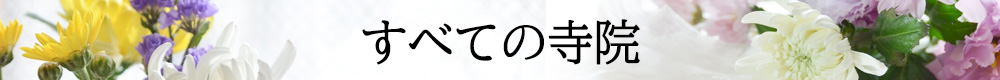
東北

かんのんじ
観音寺(青森県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

岩手県の寺院(岩手県)


 35,000円
35,000円
 50,000円
50,000円

みんなの寺(岩手県)

 55,000円
55,000円
戒名授与できません

常徳寺(秋田県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

こうふくじれいえん
興福寺霊園(宮城県)


 55,000円
55,000円
 ご相談
ご相談 
なんせんじ
南泉寺(山形県)


 35,000円
35,000円
 55,000円
55,000円

福島県の寺院(福島県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円
関東

しんこうじ
真光寺(栃木県)
 29,000円
29,000円
 ご相談
ご相談 
あんようじ
安養寺(栃木県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

上毛高原メモリアルパーク(群馬県)

 30,000円
30,000円
戒名授与できません

じょうきんじ
常金寺(埼玉県)
 30,000円
30,000円
 ご相談
ご相談 
頼忠寺・鏡ヶ浦霊園(千葉県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

成田山木更津教会新宿不動堂(千葉県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

へんじょういん
遍照院(東京都)


 50,000円
50,000円
 ご相談
ご相談 
宝清寺別院蓮華教会(東京都)


 25,000円
25,000円
 45,000円
45,000円

じょうこうじ
浄光寺(神奈川県)

 中48000
中48000 中サイズのみの取扱い。

ほうぞうじ
寳増寺(神奈川県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

観音寺(神奈川県)


 35,000円
35,000円
 55,000円
55,000円

清岩寺(神奈川県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円
中部

きんせんじ
金泉寺(新潟県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

ちょうけいじ
長慶寺(福井県)


 25,000円
25,000円
 35,000円
35,000円

しんしょういん
真照院(静岡県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

長月寺(静岡県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

あんらくじ
安楽寺(愛知県)
※ビデオがあります。


 35,000円
35,000円
 55,000円
55,000円

じょうせんじ
浄泉寺(愛知県)
※ビデオがあります。


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

えんづういん
円通院(愛知県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

せんこうじ
善光寺(愛知県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

ぜんきゅうじ
全久寺(愛知県)
※ビデオがあります。


 25,000円
25,000円
戒名授与できません

みょうふくじ
妙福寺(愛知県)

 55,000円
55,000円
 75,000円
75,000円

にょいりんじ
如意輪寺(愛知県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

えんぷくじ
円福寺(岐阜県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円
近畿

伊賀の里自然墓苑/滝仙寺(三重県)


 28,000円
28,000円
 48,000円
48,000円

さいほううじ
西方寺(三重県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

伊勢湾海洋散骨 合同会社いのり(三重県)
 34,800円
34,800円

せいりんじ
清林寺(滋賀県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

ほんしょうじ
本昌寺(京都府)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

りゅうえんじ
龍淵寺(京都府)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

せんぷくじ
泉福寺(京都府)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

えいしょうじ
栄照寺(京都府)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

みょうぎょうじ
妙行寺(京都府)


 25,000円
25,000円
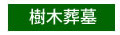 樹木50000
樹木50000 
だいしじ
大師寺(大阪府)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

智積院/河内長野中央霊園(大阪府)

 30,000円
30,000円
戒名授与できません

こうじょうじ
光乗寺(大阪府)
 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

たいしょうじ
泰聖寺(大阪府)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

ようこくじ
養谷寺(大阪府)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

ほうりんじ
法輪寺(大阪府)


 28,000円
28,000円
 48,000円
48,000円

こうきょうじ
幸教寺(大阪府)


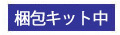 30000 中サイズ
30000 中サイズ 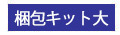 50000 大サイズ
50000 大サイズ 
さくらメモリアルパーク(大阪府)


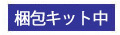 55,000円
55,000円
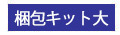 100,000
100,000 
かんのんじ
観音寺(兵庫県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

ふくおうじ
福王寺(兵庫県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

えんしょうじ
圓勝寺(兵庫県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

いっしんじ
一心寺(和歌山県)
 80,000円
80,000円
 130,000
130,000 
ちょうとくじ
長徳寺(和歌山県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円
中国

じぞういん
地蔵院(鳥取県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

みょうせんじ
明泉寺(島根県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

かんせんじ
観泉寺(岡山県)

 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円

あさばられいえん
浅原霊園(岡山県)

 50,000円
50,000円
戒名授与できません

なんせんじ
南泉寺(広島県)

 50,000円
50,000円
戒名授与できません

じゅんきょうじ
順教寺(広島県)


 50,000円
50,000円
戒名授与できません

やくおうじ
薬王寺(広島県)


 70,000円
70,000円
 90,000円
90,000円

こんごういん
金剛院(広島県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

己斐城山メモリアルヒルズ(広島県)

 50,000円
50,000円
戒名授与できません
四国

こうみょうじ
光明寺(愛媛県)


 50,000円
50,000円
 80,000円
80,000円
九州

こがれいえん
古賀霊園(福岡県)

 50,000円
50,000円
戒名授与できません

たんじょういん
誕生院(佐賀県)


 50,000円
50,000円
 70,000円
70,000円

しんぎょうじ
信行寺(熊本県)


 60,000円
60,000円
 80,000円
80,000円

いっしんじ
一心寺(大分県)


 30,000円
30,000円
 50,000円
50,000円
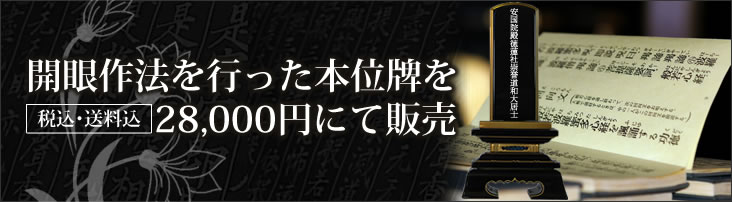
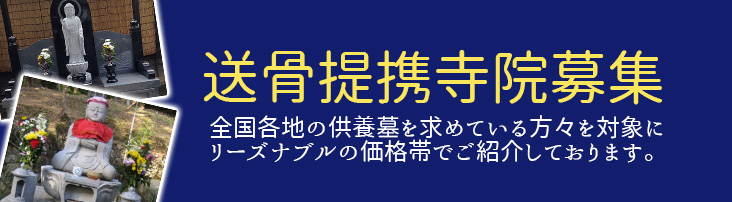
私ども「永代供養ネット」では、全国各地の寺院様の永代供養墓の販売をインターネットでお手伝いさせていただいております。
近代の傾向としては、先祖代々に守り続けてきたお墓をできる事ならずっと守り続けていきたいものですが、
少子化や核家族化が進む現代では、非常に難しい時代になってまいりました。
今後の利用者要望としては、一般的なお墓とは異なり墓石代がかからない永代供養墓などの需要がどんどん高まるものと思われます。
永代供養ネットでは全国各地の供養墓を求めている方々を対象に、リーズナブルの価格帯でご紹介しております。
菩提寺のある方(檀家になられている方)は当サービスはご利用頂けない場合がございます。